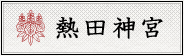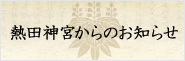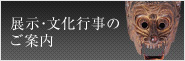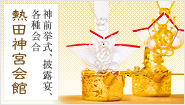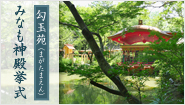今月の祭典・行事
熱田神宮では主だった祭典・神事だけでも年間およそ七十を数えます。こちらのページでは、当神宮で名高い祭典や由緒深い神事、
ならびに行事をご紹介します。
05月の祭典・行事のご案内
践祚改元奉告祭並に月次祭
令和1年05月01日(水)
舞楽神事
令和1年05月01日(水)

新緑に映える平安の雅
舞楽神事(ぶがくしんじ)
午前10:30~午後3:00 神楽殿前庭
神楽殿前庭に舞台を設け、当神宮職員及び熱田神宮桐竹会(祭典の奏楽奉仕団体)会員の奉仕により、舞楽を熱田大神様に奉納します。
社伝によると平安時代初期頃にはすでに当神宮で行われていたこの神事は、拝観者を絢爛優美の世界に誘います。
※ 演目は、振鉾(えんぶ)・賀殿(かてん)・地久(ちきゅう)・春庭花(しゅんていか)・白濱(ほうひん)・迦陵頻(かりょうびん)・蘭陵王(らんりょうおう)・落蹲(らくそん)長慶子(ちょうげいし)の計9曲です。
酔笑人神事
令和1年05月04日(土)

神主さんが歓喜笑楽
酔笑人神事(えようどしんじ)
午後7:00 境内各所
俗に「オホホまつり」「於賀斯(おかし)まつり」とも呼ばれます。祭員各自が神面を装束の袖に隠し持ち、内2人が袖の上から中啓で叩いて「オホ・オホ」と唱え、笛を合図に全員が大声をあげて笑う神事です。神事は影向間社・神楽殿・別宮・清雪門の4ヶ所で行われます。
※ この神事は、故あって天智天皇7年(668)から皇居に奉斎されていた草薙神剣が、天武天皇朱鳥元年(686)に再び当神宮に還座され、当時の神宮関係者が歓喜笑楽したという故事を今に伝えるものです。
神輿渡御神事
令和1年05月05日(日)

王朝絵巻を今に再現
神輿渡御神事(しんよとぎょしんじ)
午前10:00 本宮~正参道~西門
雅やかな装束を着けた約100名の奉仕者が御神宝を捧持し、神輿(みこし)を中心に行列を整え、本宮から正参道・南門を経て鎮皇門(ちんこうもん)跡の西門まで進み、遥かに皇居を望み、皇室の御安泰と国家の隆昌を祈念する祭典を行います。
※ この神事は、草薙神剣が皇居から当神宮に還座された時の御神託にもとづいて、鎮皇門から都の方を御覧になって皇城鎮護のお祭りを斎行した故実を今に伝えるものです。
豊年祭(花のとう)
令和1年05月08日(水)

今年の作柄は如何に?
豊年祭-花の撓(はなのとう)
午前8:00 本宮(おためしは西楽所)
この祭典は、日本武尊が御東征の折、当地方に農耕・養蚕・培綿の技術を伝えられた御神徳を称えるものです。
県内各地の農業関係者等は、祭典後西楽所で奉飾された陸田の畑所と水田の田所との「おためし」
(模型)、或いは当神宮で頒布する絵図を見て、自ら今年の作柄を占います。「おためし」は13日までご覧いただけます。
※ 祭典日から5月中旬までは、境内には苗や植木・家庭用品等を売る市が立ち並び、多くの参拝者で賑わいます
御陵墓祭
令和1年05月08日(水)
熱田講社春季大祭
令和1年05月09日(木)

熱田講社の春まつり
熱田講社春季大祭
午前11:00 本宮
愛知県を中心に全国各地の崇敬者を結集して組織した、「熱田講社」の春季大祭を執り行います。この日は約30,000名の講員の代表約1,000名が祭典に参列し、御神徳の宣揚と産業殖産、家業の繁栄とを祈ります。
御衣祭
令和1年05月13日(月)

神様のころもがえ
御衣祭(おんぞさい)
午前11:00 本宮
午前10時半、機殿(はたどの)の有る港区築地神社の奉賛会会員に捧持された御衣御料(おんぞごりょう)が東門に到着。ここから「大一御用」の大幟を先頭に、御衣奉献使が神御衣奉献会会員・稚児等約300名を従え、華やかな行列を整え本宮に至り進み、御神前に御衣御料を供します。
御衣奉献使は、㈱名古屋三越 笠原慶弘 氏です。
高座結御子神社例祭宵宮祭
令和1年05月31日(金)

井戸をのぞいて成育祈願
高座結御子神社例祭宵宮祭
午後5:00 高座結御子神社(境外摂社)
「虫封じ」「井戸のぞき」で知られ、子育ての神様として信仰が篤い高座結御子神社の例祭の宵宮祭を行います。 午後5時からの祭典にあわせ、町内からは子供獅子が多数集まり、我が子の無事成育祈って子供に井戸をのぞかせたり、巫子の振る鈴でお祓いを受けたりする親子づれのほほえましい姿が境内一円で見受けられます。
※本日から明日の例祭にかけて参道に露店が軒を連ねるこのお祭りは、当地方で一番早い夏祭りといわれています。